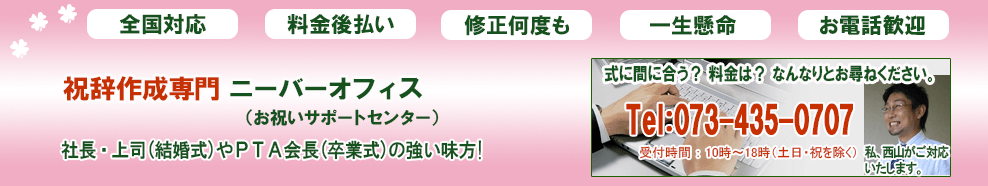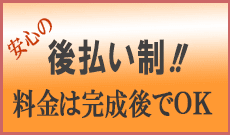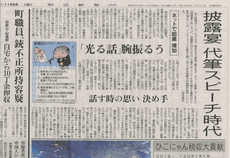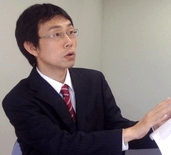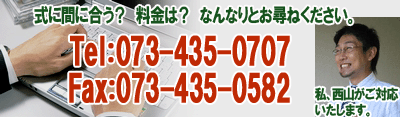骨を作る人、紙を貼る人、絵を描く人。
江戸時代、傘ひとつ仕上げる仕事においても、それぞれが役割を分担していました。どのような賃金配分でそれが成り立っていたのかまでは、詳しくないので分かりかねますが(ご興味持たれた方は是非お調べくださいませ)、
でも生活は出来てはいたのでしょうね。つましくとも暮らしはどうにか営めた。
買う側からすれば「傘」はただただ単体の商品ですから、わざわざ部品ごとにバラバラに解体して考え直したりする人は稀でしょうからね、ひとつの「傘」の後ろ側にそんなにもたくさんの人の手が関わっているだなんて、想像することは容易ではない。むしろ、傘は傘屋さん(という単一の存在)が作って売っているのだ、と考えるほうがスマートですよね。
この感覚。素朴な驚きが横たわっているし、そのあとにはじんわりと「素敵だなあ~」って思えてくる、このほっとする感じ。何に由来しているのでしょうか、この感覚。
思うに、“ひとつのことを分け合う”という点に、理屈ではない安堵感を得ているからかも知れません。
みんなで関わる、そんでもって、みんなが均等に幸せになる。
でもそもそも日本人、というより明治時代より遡ることずっと古来からの「大和民族」としての“血”には、この「みんなで」という共同体意識がしっかり根付いている気がしますし、それが現代ニッポン人においても息づいてるって証拠なのかも知れませんね。
なんてね、堅っ苦しいことを書き並べてみましたけど、ようするに「シェアって心地いいよね?」ってことなんです、言いたいことって(笑)。
そう。「シェア」、よく耳にしますよね、「シェア」。分け合う。
大皿料理を“シェア”する、駐車場管理の一台の自動車を時間“シェア”して利用する、ルームの賃料だって“シェア”して住んじゃうし、景気が良くなくなって失われちゃったここ十数年だの二十年だのの間に誕生した新しい思想「ワーク・シェアリング」、、、、、、
ん? これってほんまに、新しい??
ひとつの仕事を、それこそそれまではひとりで担当していたような単体の仕事を、内容を分割したり時間で区切ったりして、幾人かで分担してこなす。
これって要するに、江戸時代の傘の仕事と同じことじゃないでしょうか?
つまりは温故知新?
まあ小賢しい理屈はさておき、現代の仕事分担は分担した分、賃金も減っちゃうけれども、でも、考え方ひとつで非常に微笑ましい、気持ちの優しくなれるほっこりとした人間関係を育んでゆけるのでは、などと思うのですね。
苦労を知らない人間の理想論に過ぎないかも、ですけれど。
ただ、今も世の中には、自分たちが何気に生活している中ではなかなか思いの寄らない、びっくりするようなニッチな産業ってのが現実に存在していて、それこそ“傘は傘屋さんが”的な発想のままだと本当に想像の及ばないような分野の生業があるのです。
そうゆうの、想像したり調べたりするのって、なんだかワクワクいたしませんか?
トイレ掃除はあなたの分担、野菜を切るのはわたしの担当。
なんてシェアも考え方ひとつで、日々の暮らしを円滑に運営する、素敵でほのぼのとした彩(いろどり)になるってものでしょうし。
(ちょっと強引な締めくくり、ですが)