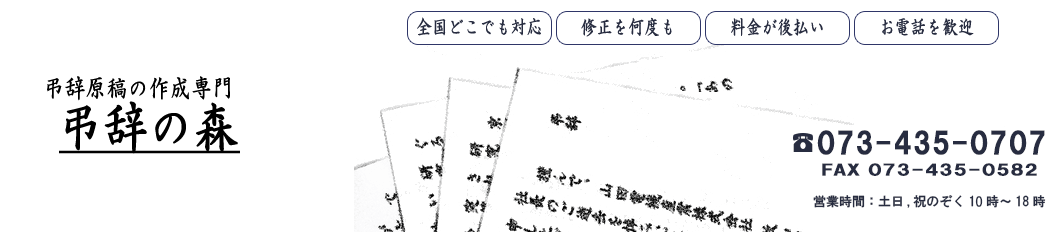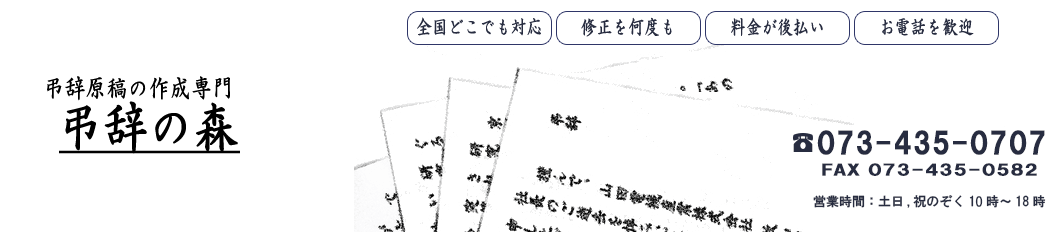前回の前編では、「故人の人柄に何を思う?」と題して、故人の訃報に接したときのお気持ち、生前の故人の活躍ぶりなどをうかがいました。
前編は下記でご覧いただけます。
葬儀委員長の挨拶(弔辞)〜前編「故人の人柄に何を思う?」
また、このインタビューを元に作成した原稿は下記でご覧いただけます。
葬儀委員長の挨拶 例文(合同葬だが実質は社葬)
今回は後編です。
創業者である故人亡き後、会社はどのようになっていくのか、していくのか。
そのほか、なぜほぼ社葬に近い合同葬になったのかや葬儀当日のことについて、細やかにお伺いしています。
最後のところで、葬儀委員長である水野氏が、改めて仕事のことを話したいとおっしゃって、決意表明にも似た思いを述べているのが印象的です。
それではどうぞ。
後編「故人亡き後のこれからの会社」
――これからは故人がもういません。今、あらためて、これからこんなふうにやっていかなければいけない、生きていかなければいけないという、お思いのところはありますか?
会長が創業されたこの会社は、企業会社、開発企業として存在していまして、お客様が困ったときにはフードロールに相談しろ、みたいな、駆け込み寺的な位置付けで、そのような雰囲気をずっとつくられてきました。こういう思いを形にしてつくった商品が評価されれば売れますし、つくってきたこのスタイルを守り続けたいということは1つあります。私どもは裏方の会社です。メーカーさんと販売会社さんとの間に立って、かゆいところに手が届くような、大手さんができないようなレスポンスと対応力で、こだわった商品をつくりあげたい、お客さんの思いをきちんと形にしたい、というモットーを持っています。
――そこの部分しっかり引き継いでいくということですね。
そうですね。生前には、皆と酒を飲み、談笑しながら、いずれ自社商品として、自信を持って世に出せる商品をつくりたいという夢を語っていました。たとえば、無名だったアサヒビールが、辛口のスーパードライを出してヒット商品になり、一躍ときの会社になったように、うちも無名の会社かもしれないけれども、そういうヒット商品をつくれば、会社は変わる。だから頑張ろうよ、ということはよく言っていました。
――その思いを引き継いで、寂しさもあり、やっていかなければという責任もあり、いろいろな思いですね。最後に、故人の呼び方なのですが、水野様は普段、何と呼んでいらっしゃいますか。
会長です。
――それでは、葬儀のご挨拶の日のタイミングや長さなのですが、おそらく葬儀委員長という立場からしますと、あまり長くないほうがよさそうですか。
当日は、ちょうど開式の挨拶のあとになりますので、お経を読み上げる前、皆さんがまだお集りになってすぐの直後にもう、ご挨拶をさせてもらうというタイミングです。
――そうなるとおそらく、5分6分では、少し長いですね。
長いと思います。やはり3分以内ぐらいというレベルではないかという話はされていました。
――あと、故人のご家庭が少し複雑ということなのですが、家族のことには触れないほうがいいですか。たとえば、残された遺族は、というようなお話はしないほうがいいでしょうか。
それはしてもいいと思います。喪主としてたぶん話はされると思います。私としては、そのへんはバランスを取っていただいて、いや別に触れても大丈夫ですよ。話としては、前妻の家族が喪主をやっていて、本妻はうちの会社にいるのですが、喪主ではないということです。
――いろいろなパワーバランスがあるのですね。
それは会長のプレーボーイがたたって、要は最後死ぬまでわがままをやり通したような感じです。俗に言う愛人がいまして、その者が身の回りを全部やっていました。
――今となっては、武勇伝として話されることですね。
それはもう、知っている人は知っているのです。そのあたりで、あえて社葬にするしかないぐらいの感じです。ただ、やはり学生時代には、それなりの成績も収めていたり、しっかりされていて、魅力のある方ですから、華やかなことに関しては何の抵抗もないのです。ですから、最期はあたたかく、華やかに送り出したいということを考えると、個人葬をやっても誰も参列しませんし、誰が陣頭指揮を取るのかという感じになりかねないということは、もう分かっています。本来であれば、密葬して、そのあとに社葬という流れになるかと思います。そうすると、密葬を誰がやるのかというような支障があるのですね。であれば一緒にやりましょうと、強引に進めました。本妻は社葬でいいという意見なのですが、前妻の身内のほうは合同葬という意見ですので、そこはうまくバランスを取ろうということで、合同葬にしました。そうすると、葬儀のあとに火葬になりますので、参列した方も顔を見ることができます。やはり、故人がその場にいるのといないのでは全然意味合いが違うかなと思います。
――いい形で脚色も交えておつくりさせていただきます。
それから、あいさつでは、業者の方々も順番関係なく、思いを伝えればいいという意見もあるのですが、バランス的にどうなのかなと思っていますが、どう思いますか?
――今回の水野様のお立場で一番のポイントは、やはり葬儀委員長が、ご参列いただいている皆さまにお話する形ですので、あまり故人のことばかりを言い過ぎるというのも。
個人的には言いたいのですが、あまり言い過ぎると葬儀委員長としてどうなのかというバランスが難しいと思っています。
――あくまで、来ていただいた皆さまへの御礼を申し上げるということが一番の主旨になります。
やはり社葬ですから、葬儀委員長として、きちんと大役をやっておりますということを伝えながら、今後、引き継いだこの会社を我々がしっかりと支えていきますのでご安心くださいということを、故人に対してと、亡くなった会長に対して、あと参列に来ていただいた方にきちんと報告するような場でもあると思います。それを、それなりの言葉でお伝えしたいです。情のこもった弔辞は、そのあとに控えている方々、重鎮がいますし、最後は恐らく喪主もボロボロになると思いますので、のっけから崩してしまうとまずいかなという、そこだけが少し心配です。
――はい。やはり、合同葬の運営側に回るというところは崩さないほうがいいかもしれないですね。
ただ、あまり故人に触れなさ過ぎてもいけませんし、ありきたりの文章を棒読みしてということも嫌なので、やはり、ちょっとした武勇伝的なものもひっくるめた挨拶をしたいと思います。そこは、難しいかもしれませんが、いただいたものに私が色をつけたりはできるかなと考えていますので、そのへんのバランスをうまく取ってほしいと思います。
――そのほか、補足がありましたらお願いします。
仕事のことについて補足させてください。イメージで言うと、メーカーさんの企画や研究開発部門が別会社化したような会社です。チャレンジ精神は他よりも強いですし、他社よりもスピード感を持ちながら対応ができる、その対応力を一番の強みとして、思いを形に、ということでやっています。なかなかあるようでないような会社だとはよく言われます。そういう基礎をつくった会長の思いを、どんどん新しく進化させていこうという思いもあります。ものづくりの考え方自体は、お客さま目線ですから変わりませんが、さらにお客様の感動するようなものをつくりたいという思いです。
――そういった創業者の思いを、しっかり引き継いでいくというお気持ちも入れつつ、葬儀委員長としての立場は、崩さずない形で作成させていただきます。ありがとうございました。
※ここで登場する人物や社名は架空のもので、実際のやりとりを想定して作成したものです。
前編は下記でご覧いただけます。
葬儀委員長の挨拶(弔辞)〜前編「故人の人柄に何を思う?」
また、このインタビューを元に作成した原稿は下記でご覧いただけます。
葬儀委員長の挨拶 例文