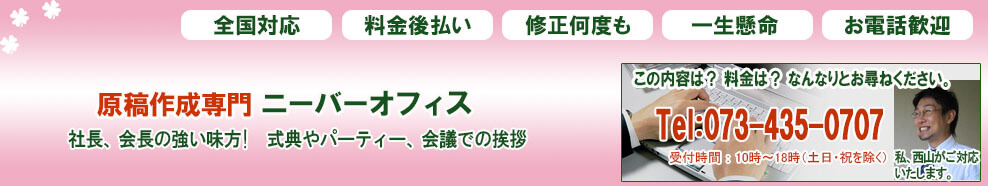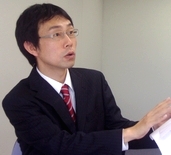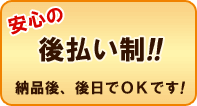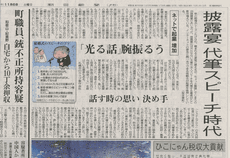【現場の安全管理にちょっと役立つ話】
まもなく安全大会の季節ですね。
元請けと協力会社が一堂に会しての安全への意思疎通を図る安全大会。ある意味で、年度初めのような気持ちになります。
さて、建設現場で「ハインリッヒの法則」って言葉、聞いたことありませんか?
有名なやつですよね。「1件の重大事故の裏には、29件の軽傷事故、さらにその背後には300件のヒヤリハットがある」ってやつです。
で、これ、なんとなく「そういうもんか〜」と受け入れられてきたわけですが、実はですね…
あれ、意外と“絶対の真理”じゃなかったんです。
実際にこの法則が出てきたのは1930年代のアメリカ。保険会社が7万件以上の事故データを調べて出した「経験則」なんですね。ただ、元のデータはもう残っていないらしく、同じ比率が他のデータでビシッと再現されたわけじゃないんです。
研究では、「なんか三角形(軽微な事故が多くて、重たい事故は少ない)っぽい傾向」は見えるんだけど、比率は業種や国、状況によってバラバラなんです。
1:29:300どころか、1:10:600だったり、1:207:2754なんてのもある。
でも、完全に無視していいかというと、そうでもない。
「軽い事故やヒヤリハットが多い職場は、将来的に大きな事故も起きやすいかもしれない」っていう考え方自体は、“傾向として”はまぁまぁ見えてるんです。
ただしそれも、「だから小さい事故を全部なくせば重大事故はゼロになる」っていうのは、ちょっと言い過ぎ。
現実はそんなに単純じゃなくて、重大事故ってのは「レアで複雑なパターン」で起きることが多い。たとえば重機の死角、複数作業のバッティング、工程の変更によるミス──いわゆる“たまたま条件がそろっちゃった”系。
じゃあ、どう考えたらいいのか?
結局、ハインリッヒの法則は「リスクを感じ取る温度計」くらいに考えておくのがちょうどいいかもしれません。
ヒヤリハットや軽微な事故がどれだけ出ているかを見ることで、「今、現場がちょっと雑になってるな」とか「声かけ・気づきの文化が弱まってるな」っていう“空気感”をつかむ材料にはなります。
でも、それを「数で管理する」って方向に行きすぎると、「報告するなよ」ってなったり、帳尻合わせの数字遊びになるのがオチ。
むしろ、報告が多い=安全に敏感で良い状態だと捉えるぐらいが◎。
最後に
1:29:300という“比率”に絶対の信頼を置く必要はないですが、
「小さいサインを見逃さないことが、大きな事故を防ぐ一歩になる」っていう感覚は、現場を預かる立場として持っておいて損はありません。
“ピラミッドのカタチは目安、でも数字は神様じゃない”──
そんなふうに、柔らかく付き合っていきましょう。
安全大会の挨拶に「ハインリッヒの法則」を盛り込む
安全大会での会長挨拶 例文はこちら