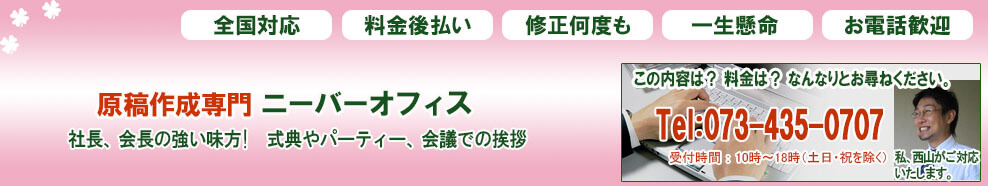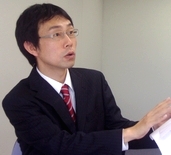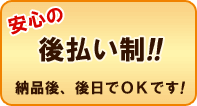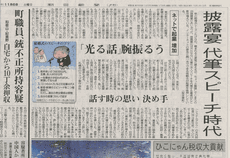解説
この式辞は、自然や音楽の比喩を用いて生徒の成長を称え、未来への指針を三つの「力」として示しています。感情の揺れに寄り添いつつ、誠実さやつながりを重視する姿勢を促す温かいメッセージです。
例文
この講堂に満ちる空気には、安堵も名残惜しさも、そして新しい季節への期待も入り混じっています。皆さんの胸の中の感情もまた、決して一色ではないでしょう。喜びと不安が同じ器に入るこの日こそ、人生が大きく動き出す合図なのです。
皆さんが入学した当初、本校の校門脇に植えられた若木はまだ細く、風に揺れていました。あれから三年が過ぎた今日、その幹は目に見えて太くなり、枝は校庭のほうにまで力強く伸びています。
毎朝その木を見上げながら、私は皆さんの成長を重ね合わせてきました。枝葉の広がりは知識の広がり、幹の厚みは経験の重み。そして根は、失敗や葛藤、対話の積み重ねです。根が広がれば、どんな嵐にも怯まずに立っていられる。皆さんは今、確かな根を持つ若木へと育ちました。
この三年間、教室での白熱した議論、実験室の集中した静けさ、グラウンドに響く歓声、演台の上で震える声、廊下で交わした何気ない挨拶。そのすべてが学校という一つの「オーケストラ」を形づくりました。
音色は一人ひとり違います。だからこそ、美しく響き合う。指揮棒を握るのは私ではありません。皆さん自身です。これからも自分のテンポで、しかし全体を聴く耳を持って、人生という演奏を続けてください。
ここで皆さんに、はなむけとして三つの「力」を贈ります。
第一に、「問い続ける勇気」。
正解が一つだけの問題は、これからどんどん減っていきます。「なぜ?」と問うことは、時に周囲の空気を揺らすかもしれません。しかし、問いこそが皆さんの羅針盤となります。迷路の中で地図を描く最初の一筆になるのです。どうか、目の前の「当たり前」に小さな疑問符を置く習慣を忘れないでください。
第二に、「つながる力」。
人は決して、自分で自分の背中を見ることはできません。だからこそ、違う視点を持つ人に学ぶのです。遠くの誰かと協働する日もあれば、隣の席の友と意見が食い違う日もあるでしょう。
そんなときは、まず相手の言葉を自分なりに言い換えて返すところから始めてください。理解は同意と同じではありません。理解なき同意よりも、敬意ある不一致を大切にしてください。
第三に、「楽しむ技術」。
努力は歯を食いしばるだけでは続きません。目標を小さく区切って達成感を味わう、失敗を「リハーサル」と呼び替える、昨日の自分にだけ勝負を挑む。楽しむことは、決して怠けることではありません。むしろその対極にあります。継続のための工夫こそ、最大の実力なのです。
皆さんの歩む進路は実に多様です。既に決まった道に胸を張る人も、これから探す人もいることでしょう。どうか意気揚々と踏み出していってください。皆さんの目の前に広がる道は、決して一本ではありません。そして、その道の「歩き方」も、いつでも自分で選ぶことができます。目標は遠くに置き、足もとは丁寧に。今日の小さな前進を言葉にして記録してください。言葉にした一歩は、必ず皆さんの地図に残ります。
これから皆さんは、数えきれない「初めて」に出会うでしょう。初めての職場、初めての研究、初めての住まい、そして、初めての孤独。
孤独という言葉の響きに不安を感じる人もいるかもしれませんが、大丈夫です。孤独は、集中と創造の前室でもあります。扉の向こうに人がいることを確かめたら、勇気を出してノックして開ければいい。助けを求めることは弱さではなく、前に進むための作法なのです。
そして、どうか誠実であってください。約束の時間を守る、感謝を言葉にする、見えないところも手を抜かない。こうした平凡に見える行いの積み重ねが、やがて皆さんの名前を信用へと変えていきます。信用は、どんな資格よりも強い通行証です。
【保護者の皆様への言葉】
【ご来賓の皆様への言葉】
卒業生の皆さん。卒業証書は、終わりの証明ではありません。学び続ける資格の第一号です。迷ったときは、入学式の日の自分を思い出してください。まだ見ぬ景色に目を輝かせていたはずです。その輝きは、間違いなく今日も皆さんの中にあります。どうか胸を張って、新たな一歩を踏み出してください。
灯台は岸辺にありますが、船が進むのは大海原です。岸を離れ、しかし光は忘れずに。
以下も読まれています↓
校長の卒業式 式辞 作成代行サービスはこちら
https://www.documedia-p.com/executive/principal/